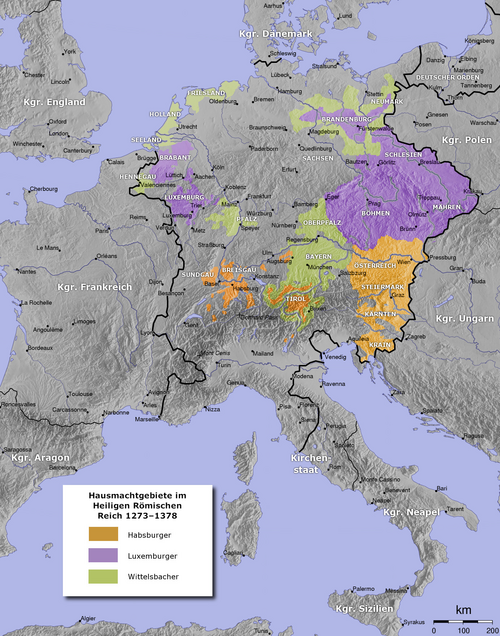いつ・どうやって成立したか─神聖ローマ帝国の「起源」とは
神聖ローマ帝国という名前、ちょっと不思議じゃないですか?「ローマ」と言いつつ、場所は主にドイツ。「帝国」と言いつつ、分裂だらけ。そして「神聖」──これは教会との関係が深い証拠です。では、いったいこの国は、いつ、誰によって、どんな経緯で誕生したのでしょうか?
この記事では、神聖ローマ帝国の起源を3つの段階に分けて、わかりやすく解説していきます。
フランク帝国の皇帝冠が「芽」
すべては「西ローマ帝国の復活」を掲げた、ある一人の王から始まりました。
カール大帝が“ローマ皇帝”に
8世紀末、ゲルマン系の大帝国フランク王国を築いたカール大帝が、ローマ教皇レオ3世から「ローマ皇帝」の冠を授かるという出来事が起こります。これは、「ローマ帝国の正統な後継者はフランク王だ」という政治的メッセージであり、キリスト教世界の秩序を象徴するものでした。
ただし帝国はすぐに分裂
カールの死後、その帝国は息子たちの代でヴェルダン条約(843年)により三分割。のちに「西フランク王国(フランス)」「中部フランク」「東フランク王国(ドイツ)」に分かれていきます。
神聖ローマ帝国はこのうちの「東フランク」が母体となるんです。
東フランク王国が“帝国”に生まれ変わる
カール大帝の後継を名乗る勢力の中で、東フランク王国だけが“ローマ皇帝位”を継ぐことに成功します。
オットー1世の戴冠が分水嶺
東フランク王オットー1世は、領内の諸侯を抑えて王権を強化し、さらにイタリアに進出。そこで教皇ヨハネス12世を支援した見返りに「ローマ皇帝」に戴冠されます。このときから、教会と皇帝が一体となる「神聖ローマ帝国」のスタイルが始まるのです。
“神聖ローマ帝国”の名称は後世のもの
当時からその名前があったわけではなく、「神聖ローマ帝国(Sacrum Imperium Romanum)」という呼称が一般化するのは13世紀以降。とはいえ、その本質──「ローマの後継者であり、神の加護を受ける国家」──は、最初から明確な理念として存在していました。
理念と現実が交錯する“帝国”のはじまり
神聖ローマ帝国は「帝国」とは言いつつも、始まりの時点から分裂国家の性格を持っていました。
“一人の皇帝”と“多数の領邦”
オットー1世の時代以降、神聖ローマ皇帝は“西欧キリスト教世界の頂点”として君臨しますが、実際には諸侯や司教たちがそれぞれの領地を支配。皇帝は“まとめ役”にすぎず、中央集権国家とはほど遠い構造でした。
“ローマの後継者”というブランド戦略
それでも「ローマ皇帝の称号」は、ヨーロッパ中で政治的な正統性と普遍性を象徴するものでした。だからこそ、オットー1世以降の王たちは、この冠にこだわり続け、「神聖ローマ帝国」という名のもとにヨーロッパの秩序を築こうとしたのです。
- 800年にカール大帝がローマ皇帝になり、帝国の理念が生まれた。
- 962年のオットー1世の戴冠により、東フランク王国が制度的に“帝国化”した。
- 帝国は最初から分裂国家でありながら、“ローマの後継”としての権威を保とうとした。