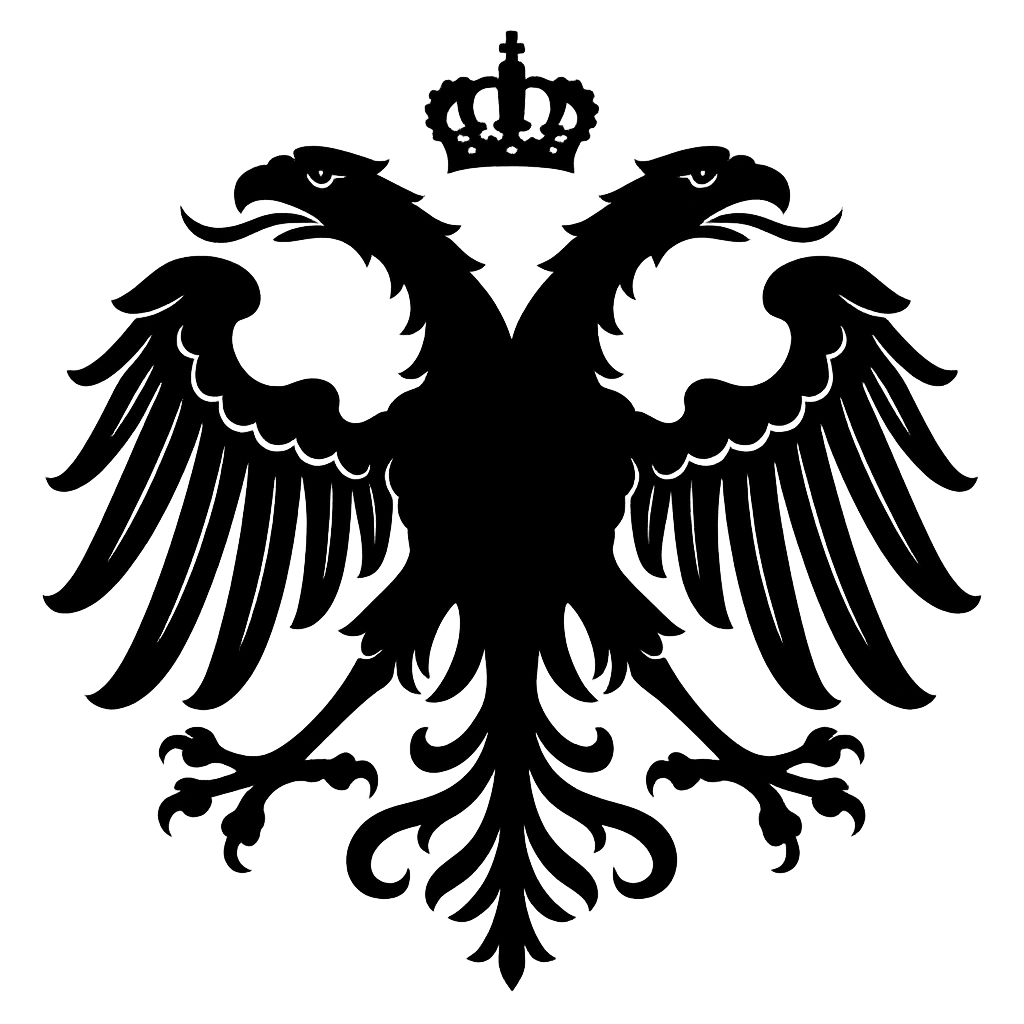ライバルか、血縁か?神聖ローマ帝国とフランスの関係
ヨーロッパの中世~近世史を語るうえで、常にセットで登場するのが神聖ローマ帝国とフランス王国。お互い西と東の「大国」として、しばしば対立していたように見える一方、実はけっこう血がつながってたり、利害が一致したりする場面も多かったんです。今回は、この2つの国の“ややこしくも切れない関係”を、時代ごとにひもといてみましょう。
もとは同じフランク王国から分裂した
そもそも、神聖ローマ帝国とフランス王国は兄弟みたいな存在だったんです。
カール大帝の死後に三分割
800年に戴冠したカール大帝(742 - 814)が築いた大帝国(カロリング帝国)は、死後に3人の孫によって分割されました。これがいわゆるヴェルダン条約(843年)です。
西フランク王国→フランスへ
この分割のうち西側が、のちのフランス王国に進化します。パリ周辺を中心に王権を確立していきました。
東フランク王国→神聖ローマ帝国へ
そして東側は、10世紀にオットー1世が皇帝戴冠を受けて神聖ローマ帝国となります。つまり、ルーツをたどれば元は“同じ国”だったわけです。
中世ではライバル関係が強まる
時代が下ると、両者の距離はどんどん遠くなり、ついには対立軸として語られるようになります。
領地争いと国境問題
特に神聖ローマ帝国西端のロレーヌ公領・アルザス・ブルゴーニュなどは、フランス王国との“はざま”にあって、どちらが支配権を持つかでたびたび争いが起きました。
教皇をめぐる立場の違い
フランスはカトリックに忠実な一方、神聖ローマ帝国は皇帝と教皇の対立(叙任権闘争)でゴタゴタする場面が多く、宗教面でも微妙な距離があったんです。
十字軍でもすれ違い
第2回十字軍などでは、フランス王ルイ7世と皇帝コンラート3世がともに参加したものの、戦略の違いで不協和音も。共闘といっても“一枚岩”ではありませんでした。
近世では血縁と政略の入り混じり
近世に入ると、両者の関係は単なる「敵対」から、もっと複雑な利害調整へと移行していきます。
ブルゴーニュ系とハプスブルク家
フランス王家の血を引くブルゴーニュ公国が、のちに神聖ローマ皇帝側に取り込まれたことで、フランスと帝国は領土的にも政治的にも一層入り組んだ関係に。
ハプスブルクvsヴァロワの対立
16世紀にはハプスブルク家の皇帝カール5世(1500 - 1558)と、フランス王フランソワ1世が激しく対立。これが「イタリア戦争」として何十年にもわたり繰り広げられました。
三十年戦争では敵として介入
宗教戦争である三十年戦争(1618〜1648)では、カトリック国であるにもかかわらずフランスはプロテスタント側を支援。なぜなら「皇帝の権威が強まること」を恐れたからです。
- 両者はもともと同じフランク王国から分かれた:ヴェルダン条約によって兄弟国家となった。
- 中世以降は国境や宗教で対立関係に:ロレーヌや教皇をめぐってしばしば争った。
- 近世には政略結婚と大戦争が絡み合った:ハプスブルクとヴァロワの対立が象徴的だった。