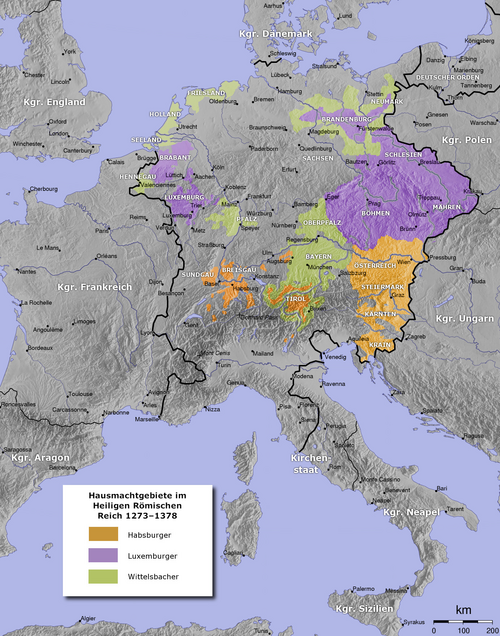| 800年 | カール大帝がローマ教皇レオ3世からローマ皇帝として戴冠(西ローマ帝国の復活) |
|---|---|
| 843年 | ヴェルダン条約によりフランク王国が分裂(のちの東フランク王国が神聖ローマ帝国の母体に) |
| 962年 | オットー1世がローマ皇帝として戴冠し、神聖ローマ帝国が正式に成立 |
| 1077年 | カノッサの屈辱:皇帝ハインリヒ4世が教皇グレゴリウス7世に破門解除を求めて屈服 |
| 1122年 | ヴォルムス協約により叙任権闘争が終結 |
| 1155年 | フリードリヒ1世バルバロッサが皇帝に即位、皇帝権強化を図る |
| 1250年 | バルバロッサの孫フリードリヒ2世が死去、皇帝位が空位となる(大空位時代の始まり) |
| 1273年 | ハプスブルク家のルドルフ1世が皇帝に選出、大空位時代の終結 |
| 1356年 | 金印勅書が発布され、七選帝侯による皇帝選出制度が確立 |
| 1438年 | ハプスブルク家のアルブレヒト2世が皇帝に即位、以後1918年まで同家が皇帝位を保持 |
| 1517年 | ルターが95か条の論題を発表し、宗教改革が始まる |
| 1555年 | アウクスブルクの和議が締結され、「諸侯の宗教、国民の宗教」が認められる |
| 1618年 | 三十年戦争が勃発(プロテスタントとカトリックの対立) |
| 1648年 | ウェストファリア条約締結、帝国の主権が諸邦に分散し、帝国の実質的な分裂が進む |
| 1701年 | プロイセン王国が成立、帝国内での影響力を強める |
| 1740年 | オーストリア継承戦争が勃発、マリア・テレジアが皇位を継承 |
| 1804年 | ナポレオンがフランス皇帝に即位、フランツ2世は「オーストリア皇帝」を名乗る |
| 1806年 | ライン同盟の成立に伴い、神聖ローマ帝国が正式に解体、フランツ2世が帝冠を返上 |
神聖ローマ帝国史の出来事─樹立~滅亡までの流れを抑えよう
神聖ローマ帝国の歴史は、ローマの復権を掲げた壮大な理想と、実際の分裂した現実とのせめぎ合いの連続でした。
皇帝、教皇、諸侯、市民…それぞれの立場が入り乱れながら進んできたこの帝国には、ヨーロッパの歴史を大きく動かした重要な出来事がたくさんあります。
この記事では、その中でもとくに歴史の転機となった出来事を厳選して紹介し、それぞれがどんな意味を持っていたのかを、わかりやすく整理していきます。
建国と皇帝制度の確立
神聖ローマ帝国の出発点は、古代ローマ帝国の“復活”という理念にありました。
800年:カール大帝の戴冠
フランク王カール大帝がローマ教皇から「ローマ皇帝」の冠を授かり、西ヨーロッパのキリスト教世界における“皇帝”の概念が復活します。これは精神的な建国の瞬間であり、神と皇帝、そしてローマという三位一体の理想が打ち立てられました。
962年:オットー1世の戴冠
ドイツ王オットー1世が教皇ヨハネス12世により戴冠され、皇帝位が正式に再制度化。これ以降、皇帝はローマ教皇の承認によって即位する形式が定着し、「神聖ローマ帝国」の制度が確立されていきます。
皇帝と教皇の対立
「神」と「権力」の両方をめぐる対立は、帝国の構造に大きな影響を与えました。
1077年:カノッサの屈辱
ハインリヒ4世とグレゴリウス7世の叙任権闘争の中で、皇帝が雪の中で教皇に赦しを乞うという衝撃的な事件が発生。皇帝の権威が揺らぎ、教皇優位の流れが決定づけられます。
1122年:ヴォルムス協約
皇帝と教皇の妥協により、叙任権闘争が一応の終結。皇帝は世俗権を、教皇は宗教的権威をそれぞれ再確認する内容で、政教分離の先駆けともいえる重要な合意でした。
帝国制度の整備
権力が分散する中で、皇帝の正統性や帝国の構造を支える制度が整っていきます。
1356年:金印勅書の発布
カール4世によって出されたこの勅書は、7人の選帝侯が皇帝を選ぶという明確なルールを定め、皇帝選出を制度的に安定させました。同時に、選帝侯の地位と自治権を強化し、帝国の“分権構造”が決定づけられました。
1495年:帝国改造令と帝国最高法院の設置
皇帝マクシミリアン1世のもと、帝国法廷や常設議会などが整備され、帝国内に統一的な法秩序を築こうとする試みが始まります。とはいえ、諸侯の自立を前提とした折衷案でもありました。
宗教改革と帝国の分裂
16世紀、帝国は大きく宗教で揺れます。
1517年:ルターの95か条の提題
マルティン・ルターがヴィッテンベルクで贖宥状販売に抗議したことで宗教改革が始動。この運動はドイツ語圏に瞬く間に拡がり、帝国の宗教的統一を破壊します。
1555年:アウクスブルクの和議
「領主の宗教が領民の宗教」──この原則によって、一応の宗教的和平が実現。ただし、帝国が公然と宗教的に二分化されることにもなり、対立は内包されたままでした。
帝国の終焉
帝国は最後まで形式を保ちつつ、ゆるやかに消滅へ向かっていきます。
1618~1648年:三十年戦争とヴェストファーレン条約
宗教と政治が絡み合った大戦争の結果、帝国は壊滅的打撃を受けます。1648年の条約で皇帝の権限は大幅に制限され、各領邦の独立性が法的に認められることに。帝国は名目上の連合体に近づきました。
1806年:帝国の正式解体
ナポレオン戦争の激動の中で、皇帝フランツ2世が退位を表明し、帝冠を返上。こうして千年近く続いた「神聖ローマ帝国」は、ついに歴史の幕を閉じました。
- 建国と戴冠(800・962年):ローマ皇帝位の復活と、教会との共存体制が始まった。
- 叙任権闘争(11~12世紀):皇帝と教皇の権力闘争が、政教分離の原型をつくった。
- 金印勅書(1356年):選帝侯制度が整い、分権化が制度化された。
- 宗教改革と三十年戦争(16~17世紀):宗教対立が帝国の分裂と戦争をもたらした。
- 帝国の解体(1806年):ナポレオン戦争を契機に、帝国は正式に終焉を迎えた。