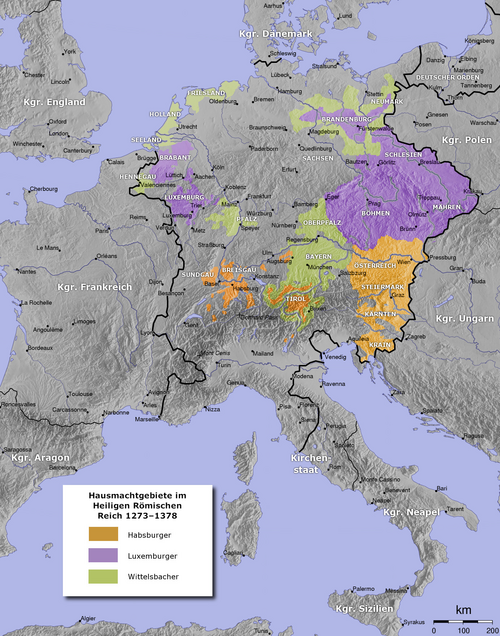神聖ローマ帝国がシュタウフェン朝で中央集権化した理由
神聖ローマ帝国の中でも、とりわけシュタウフェン朝(1138年~1254年)の時代は、皇帝が「帝国をひとつにまとめよう」と本気で中央集権化を目指した時代でした。でもそもそも、なんでこの時期だけそんな野望が燃え上がったのか?そこには、当時の国際情勢や帝国内の事情、皇帝個人の野心など、さまざまな要因が絡み合っていたんです。
この記事では、シュタウフェン朝が中央集権化に舵を切った理由について、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。
帝国内の分裂を止めたかった
まず大前提として、当時の神聖ローマ帝国はかなりバラバラでした。皇帝が立て直そうとしたのも無理はなかったんです。
ザリエル朝の末期が混乱していた
シュタウフェン家の前の王朝──ザリエル朝の終盤では、皇帝と諸侯・教会の対立が激化。とくに叙任権闘争(皇帝が司教を任命できるかどうかをめぐる争い)によって、皇帝権はガタ落ちに。
この「皇帝なめられ期」を引きずっていたため、次の王朝では「もう一回、皇帝の威厳を取り戻そう」という気運があったわけです。
領邦が強くなりすぎていた
帝国はもともと諸侯や教会の土地がバラバラに散らばる構造でしたが、12世紀にはそれぞれの領邦がますます力をつけていました。皇帝が放っておくと、諸侯が“ほぼ王様”状態になってしまう。
だからこそ、皇帝としては「もう一回、帝国全体をまとめ直す」必要があったのです。
イタリア政策による財政と威信の強化
シュタウフェン朝の皇帝たちが力を入れたのがイタリア政策──これが中央集権化のもうひとつの柱になります。
豊かなイタリア都市を支配したかった
神聖ローマ皇帝には、「ローマで戴冠する=正統な皇帝として認められる」という価値観がありました。でもローマに行くには北イタリアの諸都市(ミラノ・パヴィア・ヴェローナなど)を通らなければならない。そしてこれらの都市は、当時すでに経済的にメチャ強かったんです。
つまり、イタリアを掌握すれば経済力も軍事力も一気に増す。この狙いがあって、シュタウフェン朝の皇帝たちは南下していったんですね。
シチリア王国との同君連合
とりわけフリードリヒ2世は、ドイツ王でありながらシチリア王でもありました。シチリア王国は行政・税制・軍事が整った“近代的”な王国で、彼はこのモデルをドイツ側にも輸入したかった。
言ってしまえば、南の強力な拠点を持った上で、北のドイツを統制しようとしたわけです。
皇帝個人のカリスマと理念
制度だけでなく、「人」もまた大きな推進力でした。シュタウフェン朝には、なぜか妙にスケールの大きい皇帝が集中していたんです。
フリードリヒ1世バルバロッサの強権路線
フリードリヒ1世(1122頃 - 1190)は、その赤髭(バルバロッサ)とともに“帝国の顔”として知られる人物。諸侯たちをおさえつけ、法と秩序の回復を目指して動きました。
彼は「帝国とは神が定めた秩序である」と考え、法体系を整え、都市にも皇帝直轄の特権を与えるなど、中世型中央集権の芽を育てたんですね。
フリードリヒ2世の異彩と実行力
そして孫のフリードリヒ2世は、そのカリスマと独創性で異彩を放ちます。彼はアラビア語や自然科学に通じ、「皇帝は普遍的支配者であるべき」と考えていました。
そのため、宗教にも貴族にも忖度しない超然的な中央集権国家を夢見て、法典整備、官僚制の導入、徴税制度の統一など、いま見てもかなり現代的な改革を進めたのです。
- ザリエル朝の混乱を修復したかった:諸侯や教会にナメられた皇帝権を立て直すため
- イタリア支配が経済・軍事の鍵だった:北イタリアとシチリア王国が中核になった
- カリスマ皇帝たちの理念が後押し:バルバロッサとフリードリヒ2世の影響力が大きかった